『ラザルス』なぜ批評家は酷評?Rotten Tomatoes 42%と「賛否両論」の真相、サム・クラフリンの功績を徹底分析!
『ラザルス』、なぜか海外で「歴史的酷評」を受けている件。
こんにちは!YOSHIKIです。
先日配信された『ハーラン・コーベン/ラザルス』、ご覧になりましたか?
メインの記事(『ハーラン・コーベン/ラザルス』結末の真相を徹底考察!…ネタバレ解説・レビュー)では、僕自身「欠点だらけ、でも目が離せない(総合7.6点)」、特に主演サム・クラフリンの演技は10点満点!と、その中毒性について熱く語りました。
しかし、配信後、海外の批評サイトを見て僕は凍りつきました。
「Rotten Tomatoes 批評家スコア 42%」
「Metacritic スコア 53/100」
これは、ハーラン・コーベン作品史上、最も低い評価です。
(出典:Screen Rant [1], [2], [3])
なぜ、僕(7.6点)や多くの視聴者(RT観客スコア68%)が熱狂した作品が、批評家からはこれほどまでに「悲惨」「怠惰な脚本」と酷評されているのでしょうか?

この記事は、YOSHIKIのメイン記事を補完する「徹底・評価分析記事」です。
この「批評家(酷評) VS 視聴者(熱狂)」という矛盾を、制作背景や海外の具体的なレビューを基に徹底的に解き明かしていきます!
🟡第1部:「批評家」はなぜ『ラザルス』を酷評したのか? (Rotten 42%の理由)

まず、なぜプロの批評家たちは本作に「Rotten(腐っている)」の烙印を押したのか?
リサーチで判明した、彼らの具体的な批判点を見ていきましょう。
批判①:「安易すぎる」超常現象(幽霊)の使い方
批評家が最も問題視したのが「幽霊」の扱いです。
The Guardian紙のルーシー・マンガンは、本作を「全くもって悲惨」と断じ、「(主人公が窮地に陥るたびに都合よく幻影が現れるのは)作り手が視聴者を侮辱するのに近い、怠惰な脚本だ」と厳しく批判しています。
(出典:The Guardian [3])
ミステリーの緊張感を、超常現象という「安易な飛び道具(デウス・エクス・マキナ)」で台無しにしている、というのが最大の批判点です。
The A.V. Clubも、この設定が「怠惰な心理ドラマ」のための「松葉杖」として使われていると断じました。
(出典:The A.V. Club [12])
批判②:ツッコミ所満載の「プロットの穴」と論理崩壊
「自殺した父の手を鑑識にかけない警察」「精神科医が犯罪現場の壁を斧で破壊する」など、物語の整合性を無視した「ありえない展開」が多すぎると指摘されています。
RogerEbert.comは「どんでん返しが、観客を驚かせるためだけにあからさまに設計されており、しばしば意味をなさなくなる」と酷評。
Irish Independent紙に至っては、プロットを「全くのでたらめ(complete hogwash)」と一蹴しています。
批判③:「ひどく反復的」なペース配分
「一気見」を狙うあまり、物語が前に進まない点も批判されました。
The Guardian紙は「登場人物たちが、我々がたった今見たばかりの事柄を何度も何度も互いに語り合い…(中略)…ひどく反復的だ」と指摘。
その結果「内容が薄っぺらい」と結論づけています。
(出典:CBR (The Guardianの引用) [3])
批評家の総意:「野心は認めるが、実行が伴っていない」
まとめると、批評家たちは「心理ドラマ」「ミステリー」「超常ホラー」を融合させるという野心は認めるものの、各要素が噛み合わず、物語が破綻している、と結論づけたようです。
一方で、作品の「不気味なトーン」「ゴシックな雰囲気」といったビジュアル面は称賛されていました。
また、The Independent紙のように「奇妙で馬鹿げている」と認めつつも、「信じられないほど後を引く(moreish)」魅力があり、「視聴者を惹きつけるために精密に設計されている」と、その中毒性を評価する声も少数ながら存在しました。
🟡第2部:「視聴者」はなぜ『ラザルス』に熱狂したのか? (観客スコア68%の理由)

批評家が42%と酷評する一方、なぜ観客スコアは68%(IMDb 6.3/10)と、比較的高いのでしょうか?
YOSHIKIのメイン記事の感想とも重なる、視聴者が「ハマった」理由を分析します。
熱狂①:すべてを救った「サム・クラフリンの圧巻の演技」
本作が崩壊しなかった最大の理由。
メイン記事で僕が「演技10点」を付けた通りです。
酷評した批評家でさえ、サム・クラフリンの演技は「心に残る」と評価。
Colliderは、彼が「知的なスクリーンでの存在感」を発揮し、「複雑な感情の機微」を見事に表現したと称賛しています。
視聴者は、サム・クラフリンが演じるラズの「苦悩」に感情移入し、彼の視点で物語を追体験することで、脚本の穴を乗り越えることができました。
熱狂②:「ハーラン・コーベン」ブランドへの絶対的信頼
Netflixでの長年の成功により、「ハーラン・コーベン」の名前は「中毒性があり、どんでん返しに満ちた体験」のブランドとなっています。
批評家が「またか」と呆れる「強引などんでん返し」や「一気見させるクリフハンガー」こそが、視聴者がコーベンに求める「お約束」なのです。
実際、本作はPrime Videoで世界ランキング3位、イギリスやオーストラリアなど9カ国で1位を獲得する大ヒットを記録しています。
これは、批評家のレビューに関わらず視聴を決める「拒否権を発動させない」ブランド力が確立されている証拠です。
熱狂③:日本でも賛否両論「展開が読めない」vs「拍子抜け」
日本のFilmarksなどでも評価は真っ二つ。
「最後まで展開が読めなかった」
「ラストのどんでん返しが凄い」
という絶賛の声。
一方で、
「オカルトが強すぎて拍子抜け」
「ラストのルール無視は嫌い」
という酷評も。
この賛否両論こそが、本作が「退屈な作品」ではなく「無視できない問題作」である証拠です。
Redditなどの海外フォーラムでも、エイダンの結末を巡って活発な議論が交わされています。
🟡第3部:なぜこの「分裂」は生まれたのか? (制作者の意図)

なぜコーベンは、成功が約束されたミステリーから、酷評されるリスクを冒してまで「超常ホラー」に挑んだのでしょうか?
リサーチで判明した「制作背景」に、すべての答えがありました。
理由①:コーベン自身の「個人的な体験(父の死)」
本作の核は、コーベン自身が若くして亡くした「父親との思い出」や、「失った愛する人との再会を願う」という普遍的な感情にあります。
彼は「多くの物語でその経験を扱ってきたが、この作品では、それは直接的な表現だ」と語っています。
「悲しみ」という感情が現実と非現実の境界を曖昧にする。
この個人的な体験を描くために、彼は「ミステリー」という枠を超え、「超常現象(ゴーストストーリー)」という表現方法を“必要”としたのです。
理由②:小説原作ではない「完全オリジナル脚本」
本作は、コーベンの小説が原作ではありません。
最初から「テレビシリーズとして」書かれたオリジナル脚本です。
コーベンは
「小説として書くこともできたが、これはテレビシリーズとして見えた」
と語っており、最初から「視覚的」「不気味な質」を重視していました。
父のオフィスの「ボンド映画の悪役のよう」と評されたアールデコ調のデザインなども、この視覚的こだわりから来ています。
理由③:NetflixからPrime Videoへの「戦略的移籍」
コーベンはNetflixとの関係を維持しつつ(『Missing You』などを開発中)、本作ではPrime Videoとタッグを組みました。
これは、プラットフォームを拡大する「戦略的な多角化」です。
Prime Videoは「Netflixとは違う、独自のコーベン作品」を求め、コーベンは「新しい挑戦(=ホラー)」を行う実験場を得た。
この両者の利害が一致したのです。
🟡第4部:鑑賞後の疑問(Q&A)—「幽霊」と「続編」の謎

メイン記事の考察と重なる部分もありますが、視聴者が最も混乱した「謎」をQ&A形式で整理します。
Q1:「幽霊」は本物? ラズの妄想?
A. 「トラウマ(悲嘆)が見せた幻覚」であり、その“情報源”は「父の録音テープ」です。
本作は最終話で「合理的」な説明を提示します。
ラズは父のセッション記録のテープを強迫的に聴いており、彼の心がその「音声情報」を「視覚的な幽霊」として再構築していました。
これが、幽霊が父のオフィスにしか現れず、ラズを父と勘違いした理由です。
しかし、批評家が指摘するように、音声だけでは知り得ない視覚情報(例:母子像)も幽霊は提示しており、ここが最大の「プロットの穴」となっています。
Q2:ラスト、エイダンが殺人鬼だった意味は?
A. メイン記事で考察した通り、「暴力の連鎖は終わらない」というテーマ的結論です。
父ジョナサンの幽霊が語った「息子は結局、父親のようになる」という呪い。
ラズ(息子)はその連鎖を断ち切ったかに見えましたが、呪いは一世代飛び越え、エイダン(孫)へと受け継がれていました。
これは「衝撃のためのどんでん返し」であると同時に、「世代間のトラウマからは逃れられない」という、本作の暗く決定論的な世界観を示す結末です。
Q3:シーズン2の可能性は?
A. 限りなくゼロに近いです。コーベン自身が「完結した物語」と明言しています。
ハーラン・コーベンはColliderとのインタビューで、
「第1話で提起されたすべての疑問は、第6話で答えが出される」
と語り、本作が自己完結型の物語であることを強調しています。
彼は自身の作品でシーズン2を制作したことがなく、続編の唯一の条件は
「シーズン1と同等か、それ以上に優れたものになる」
と確信できた場合のみだ、と語っています。
キャスト(サム・クラフリンやアレクサンドラ・ローチ)は続編に意欲的ですが、クリエイターのこの哲学を覆すのは難しそうです。
あの衝撃的なラストは「続編へのフック」ではなく、「テーマ的な結論(終止符)」として受け取るべきでしょう。
🟡まとめ:批評家は「酷評」、視聴者は「熱狂」— なぜ評価は分裂したのか?
『ラザルス』の「評価パラドックス」を深掘りしてきました。
物語の整合性を重視する彼らにとって、プロット穴だらけで、超常現象をご都合主義に使う本作は「怠惰な脚本」であり、耐え難いものでした。
「一気見」の刺激と「どんでん返し」を求める視聴者にとって、サム・クラフリンの名演とコーベン・ブランドの中毒性は、脚本の欠点を補って余りある魅力だった。
この分裂は、コーベンが「父の死」という個人的な動機から、「小説原作のミステリー」という成功法則を捨て、「超常ホラー」へと意図的に挑戦した「野心」の代償だった。
結論として、『ラザルス』は、完璧な芸術品を求める「批評家の悪夢」であり、理屈抜きの刺激を求める「視聴者の麻薬」だった、と僕は結論づけます。
メイン記事で書いた僕の評価(7.6点)は、まさにこの「欠点だらけだが、止められない!」という、両者の評価のど真ん中にあったのだと再確認しました。

皆さんは、批評家派でしたか? それとも視聴者派でしたか?
ぜひコメントであなたの感想を聞かせてください!



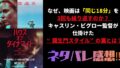
コメント