なぜ、主題歌は山崎まさよしではなかったのか?米津玄師『1991』が、アニメ版の「呪い」に与えた、もう一つの“答え”!
実写版『秒速5センチメートル』

この映画を観た誰もが、エンドロールで流れる米津玄師さんの歌声に、心を鷲掴みにされたはずです。
なぜ、主題歌は山崎まさよしさんの名曲ではなかったのか?
なぜ、タイトルは『1991』なのか?
そして、あの歌詞は、貴樹の物語をどう完結させたのか?
この記事では、そんな君たちの積年の疑問に、僕の魂を込めて、徹底的に答えていくぜーー!
🔴序論:なぜ、山崎まさよしではなかったのか?
まず、最初に言っておきたい。
この映画は、山崎まさよしさんの『One more time, One more chance』を、決して無視したわけじゃない。
それどころか、劇中歌として採用し、オリジナル作品への最大限のリスペクトを捧げている。
この事実は、新主題歌である米津玄師さんの『1991』が、過去を消し去るんじゃなく、それと対話し、共存することを意図して作られたことを、何よりも雄弁に物語っている。
この試みの中心にあるのが、僕が「1991年の協和」と呼びたい、奇跡的な偶然です。
アーティストである米津玄師さんと、監督の奥山由之さん。
この二人が、共に1991年生まれであるという事実。
これは、単なる偶然じゃないと思う。
今回のコラボレーションを方向付ける、基本原則なんです。
『1991』は単なる主題歌の枠を超えた、一つのミッションステートメント。
それは、クリエイター自身の個人的かつ世代的な原作解釈の表明であり、オリジナルが内包していた未解決のメランコリーに対する一つの応答であり、そして類稀な創造的パートナーシップの証なんです。
🔴タイトル『1991』に込められた、3つの意味!
①貴樹と明里が出会った「始まりの年」
まず、最も直接的な意味。
「1991」という年は、物語の主人公である遠野貴樹と篠原明里が、東京の小学校で初めて出会った年です。
このタイトルによって、楽曲は、物語全体の喜びと悲しみの源流となる、あの根源的な瞬間に、僕らを一気に引き戻す。
それは、貴樹の心に深く刻まれた、眩しい日常、そして大人になっても色褪せることのない「あの頃」そのものを象徴しているんです。
この曲を聴くたびに、僕らの脳裏には、あの桜並木の風景や、図書館で過ごした放課後、そして二人で分け合ったコーヒー牛乳の味が、鮮やかに蘇ってくる。
タイトルそのものが、物語への、最も強力な入り口になっているんだよね。
②米津玄師と奥山監督、二人の「誕生の年」
次に、このタイトルは、米津玄師さんと奥山由之監督が、共に1991年生まれであるという事実によって、単なる物語上の記号から、極めて個人的な「サイン」へと変わっていく。
奥山監督は、「主人公である貴樹の半生に、映像や音楽を通して僕ら自身を重ねて描くことの意味が『1991』という曲の筆跡に詰まっている」と、はっきりと語っている。
この楽曲は、彼らが自分たちの世代の経験を通して、あの物語をもう一度、見つめ直し、再構築した、その成果そのものなんです。
これは、ただのタイアップじゃない。
クリエイターたちが、「これは、僕らの物語でもあるんだ」と、力強く宣言する、所信表明のようなものなんです。
③僕らの時代の「物語」
そして最も重要なのが、このタイトルがフィクションの世界と、クリエイターの現実との境界線を、意図的に曖昧にしている点です。
米津さん自身、この楽曲が映画のために書き下ろされたものであると同時に、「わたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました」とコメントしている。
この言葉によって、僕らは気づかされる。
この物語は、単に貴樹の旅路としてだけでなく、1991年前後に生まれた、僕らの世代の経験を映し出す、一つの寓話として、考察することができるんだ、と。
あの頃感じた、どうしようもない焦燥感や、言葉にできなかった想い。
そういった、僕らの心の中に眠っている記憶を、この曲は優しく呼び覚ましてくれる。
だからこそ、『1991』は、ただの主題歌を超えて、僕ら自身の物語として、深く心に響くんだと思います。
🔴【歌詞解釈】物語とのシンクロ率120%!YOSHIKIが震えた、3つの神フレーズ!
ついに、主題歌『1991』の公式な歌詞が、全文公開されました。
僕も早速聴いたけど…もうね、震えたね。
これは、ただの主題歌じゃない。
実写版『秒速5センチメートル』の、もう一つの脚本です。
まずは、その全文を、君自身の目で確かめてほしい。
米津玄師『1991』歌詞全文
君の声が聞こえたような気がして僕は振り向いた 1991僕は生まれた 靴ばかり見つめて生きていた いつも笑って隠した 消えない傷と寂しさを 1991恋をしていた 光る過去を覗くように
ねえ こんなに簡単なことに気づけなかったんだ 優しくなんてなかった 僕はただいつまでも君といたかった
雪のようにひらりひらり落ちる桜 君のいない人生を耐えられるだろうか
どこで誰と何をしていてもここじゃなかった 生きていたくも死にたくもなかった いつも遠くを見ているふりして 泣き叫びたかった 1991恋をしていた 過ぎた過去に縋るように
ねえ 小さく揺らいだ果てに僕ら出会ったんだ 息ができなかった 僕はただいつまでも君といたかった
雪のようにひらりひらり落ちる桜 君のいない人生を耐えられるだろうか
1991僕は瞬くように恋をした 1991いつも夢見るように生きていた
出典:Uta-Net
どうですか?
この歌詞の全てが、貴樹の心の叫びそのものだったでしょ?
その中でも、特に僕の心を揺さぶった、3つの神フレーズについて、語らせてほしいです。
「いつも笑って隠した 消えない傷と寂しさを」― 貴樹の“本当の顔”
この一節は、貴樹というキャラクターの、長年にわたる痛みの本質を、完璧に言い当てている。
彼は、周りからは物静かで、クールな人間に見えていたかもしれない。
でも、その心の内側では、ずっと「消えない傷と寂しさ」を抱え、それを笑顔で隠し続けてきた。
この告白は、彼が単に過去に囚われているだけでなく、その痛みを誰にも言えず、一人で抱え込んできた、その孤独の深さを、僕らに教えてくれる。
「優しくなんてなかった 僕はただいつまでも君といたかった」― 13年越しの本心
これこそが、テーマ的に最も重要な一節だろう。
花苗の想いに応えられなかったのも、理紗との関係を深められなかったのも、彼が優しすぎたからじゃない。
彼の心の中には、ずっと、たった一つの、あまりにも純粋で、そして残酷な願いがあっただけなんです。
「僕はただいつまでも君といたかった」 この、子供のような、どうしようもない本心。
これを認めることこそが、彼が前に進むための、最初のステップだったんだなって思う。
「雪のようにひらりひらり落ちる桜」― 原作への、最大のリスペクト
そして、このサビのフレーズ。
「秒速5センチメートルは、桜の花びらが落ちるスピード」 「雪みたいだね」 原作アニメを観た人なら、誰もが覚えている、貴樹と明里の、あの美しくも切ない会話。
その、「桜」と「雪」という、二つの最も重要なキーワードを、一つのフレーズに融合させる。
これ以上ない、原作へのリスペクトと、愛に満ちた表現じゃないかーー。
米津さんは、ただ物語に寄り添うだけじゃない。
物語の魂そのものを、自分の言葉で、もう一度、僕らの心に届けてくれたんだと思います。
🔴【YOSHIKI考察】なぜ、この曲は「最後のナレーション」なのか?
アニメ版の主題歌、山崎まさよし「One more time, One more chance」との比較
アニメ版の主題歌、山崎まさよしさんの『One more time, One more chance』。
あの曲の歌詞は、「向いのホーム 路地裏の窓」「交差点でも 夢の中でも」と、相手がいるはずのない場所で、探し続けるというモチーフで貫かれている。
主人公は、別れの事実を受け入れることができず、奇跡的な再会を願う思考のループに囚われている。
時間が止まり、過去に佇み続ける心情を、徹底して描いているんだよね。
「願いがもしも叶うなら 今すぐ君のもとへ」という、あまりにも有名なフレーズ。
これは、主人公の無力さを強調している。
彼は自らの力で未来を切り拓くんじゃなく、奇跡という、自分以外の何かの力に、ただただすがるしかない。
この、どうしようもない停滞感こそが、アニメ版『秒速』が描いた、美しい「呪い」の正体だった。
貴樹の「再生」を高らかに宣言する、もう一つのエンディング
対照的に、『1991』の鍵となるフレーズは、現在の状態(「僕は元気」)と未来への意志(「これで最後の夜にするね」)の宣言です。
山崎さんの楽曲が「命が繰り返すならば 何度も君のもとへ」という、絶望的で永遠の懇願で終わるとすれば、米津さんの楽曲は、人生は繰り返されず、それを受け入れて一人で、しかし完全な自己として前進することに平穏が見出されるのだという、静かで成熟した悟りを提供する。
新しい楽曲は、オリジナルが意図的に与えなかったカタルシスをもたらす。
映画の中で、二つの楽曲が共存することで、貴樹のノスタルジックな痛みの頂点と、その痛みを乗り越えた後の精神状態、その両方が描かれる。
二つの曲の関係は対立じゃない。
「進行」なんだと思う。
『1991』は、『One more time, One more chance』という感情の旅路が、最終的にたどり着く目的地だったんだよ。
▼実写版『秒速5センチメートル』本編のネタバレ感想・考察はこちらの記事で!
🔴まとめ:この記事で伝えたかったこと!

さて、長々と語ってきましたが、最後にこの記事で解説した、主題歌『1991』の深すぎる魅力を、分かりやすく箇条書きでまとめておきましょう!
この曲を聴くまで、実写版『秒速5センチメートル』は、本当の意味で完結しない。
僕は、そう確信しています。

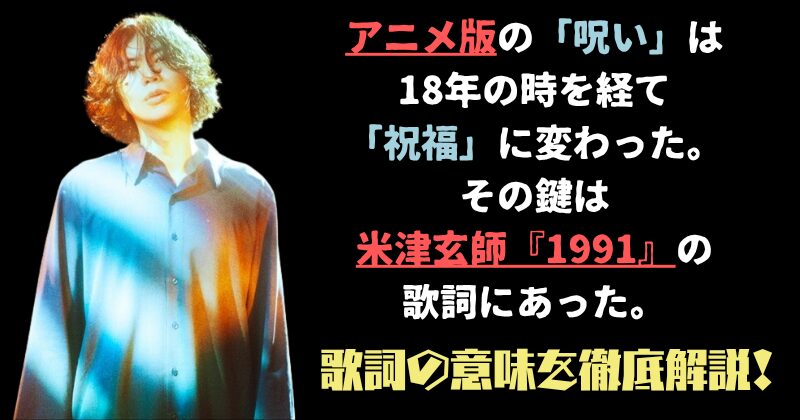
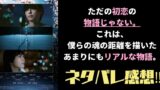

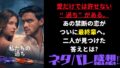
コメント